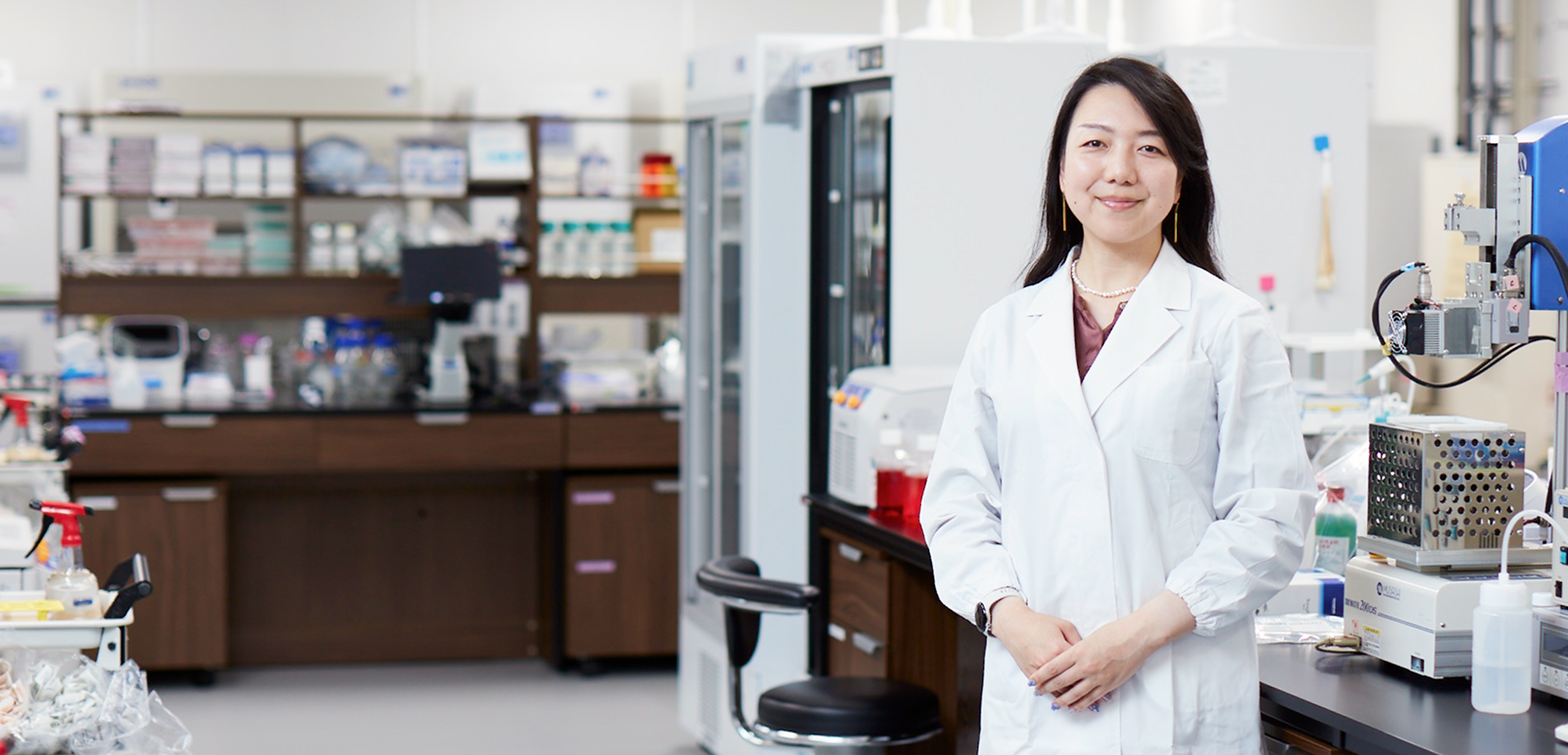
加藤 あすか0から1を生み出す現場で、培養肉という新たな食を創生
加藤 あすか:2013年京都大学農学研究科卒。2013年凸版印刷入社。医薬品包材の営業を経て2015年に研究所へ異動し、三次元細胞培養技術の研究開発に従事。産・育休を経て、現在は培養肉開発プロジェクトに所属。TOPPANと大阪大学で共同開発した、独自材料における食品グレードの量産化プロセス構築に従事。アカデミアとの連携のもと、培養肉という全く新しい食品・構造体の社会実装を見据え、技術的観点から開発方針の検討とプロジェクト推進に携わる。 業務の傍ら、2023年より大阪大学大学院工学研究科博士後期課程に入学し、「コラーゲンを用いた新規三次元細胞培養法の開発」を探求している。認定バイオインフォマティクス技術者資格保持。

形を変えて続いてきた「つくる」という感覚
2025年、大阪・関西万博。「家庭で作る霜降り肉」をテーマに展示された培養肉は、大きな注目を集めました。培養肉とは、動物から採取した少量の細胞を培養して増やし、筋組織として作り上げる“本物の肉”です。「培養肉未来創造コンソーシアム」にはTOPPANも参画しており、その展示内容に大きく貢献した一人が加藤です。
岐阜県大垣市で生まれ育った加藤は、幼い頃から手を動かして何かをつくることが好きでした。絵を描くよりも、木を切ったり、ものを組み立てたりするほうが性に合っていたといいます。
「平面よりも立体に興味があり、完成形を頭に描いてどのような形にするかを考えることが楽しかったです。」(加藤、以下同)
京都大学では農学部に進み、森林や木材について学ぶ中で受けた木材加工の授業の影響から、一人暮らしの部屋では家具を塗り替え、テレビ台を自作することも。設計し、加工し、試し、改良する。そうしたプロセス自体が、モノつくりの楽しさの原体験として残っているそうです。やがて植物分子生物学と出会い、関心は目に見えない世界へと広がっていきます。遺伝子という見えないものの操作が、形や機能など、目に見える変化として現れることに惹かれたといいます。凸版印刷(当時)を志望した理由は、研究室の先輩が凸版印刷で遺伝子解析に携わっていたこと、そして「印刷会社」という枠を超えて技術を社会に実装してきた企業であると知ったことがきっかけになりました。
「研究を研究室の中だけで終わらせるのではなく、社会と繋がったところで専門性を活かしていきたいと考えていました。この会社なら面白いことができそうだなというワクワク感が決め手になりました。」

営業で培ったセンスを武器に、研究の最前線へ
入社後、営業に配属された加藤は、医薬品包材の営業として活躍しながらビジネスセンスを磨いていきます。
「それまで漠然と『営業とは数字を追えばいいもの』と思っていましたが、利益のために非常にロジカルに意思決定をしていることに最初は驚きました。」
そして、モノつくりの視点で事業に貢献したいと思い、若手社員が自発的に新しい研究開発テーマを提案し事業化を目指す社内制度「フロントランナー制度」を活用して、三次元細胞培養技術を手掛けるグループに参加。その後、総合研究所に異動し、大阪大学に常駐する研究者として新たなキャリアを切り拓きました。
「当時、私が従事していたのは、細胞を評価する技術や、細胞を積層するための技術、コラーゲン材料の開発など、三次元細胞培養技術の基礎にあたる部分でした。」
これらの技術は後に、TOPPANが大阪大学松崎典弥教授と共同で開発した独自の三次元細胞培養技術「invivoid®」として結実するものです。
現在のメインテーマである培養肉開発プロジェクトは、三次元細胞培養技術がスピンアウトするかたちで、2023年に培養肉共同研究講座が立ち上がってスタートしました。加藤は講座そのものの設計から実験室、さらには研究室オフィスのレイアウトにまで関与しています。
「当講座も三次元細胞培養を共同研究していた松崎先生と共同で作ったものですが、先生が重視したのがオフィス入口のカウンターでした。海外の研究所、特に培養肉系のスタートアップではカジュアルな研究室やオフィスで、それこそお酒を片手に議論するというのが一般的です。そうした開けた場を用意して欲しいとリクエストされました。」


培養肉を支える「細胞の足場」
培養肉の実現性を左右する要素の一つが、細胞を育てる適切な環境です。加藤らはここにコラーゲンを見出しました。前述した「invivoid®」の要素技術のひとつです。
一般にコラーゲンとして販売されているものの多くは、実際にはコラーゲンそのものではなく、コラーゲンを分解したゼラチンなどです。コラーゲン自体は本来、独自の立体構造を持つ強固なタンパク質で、水に溶けにくく、そのままでは扱いが難しい性質があります。一方、ゼラチンはこの構造をほぐしたもので、水中でもサラサラと扱いやすく、消化しやすいため食品用途に適しています。
しかし、細胞培養の分野では事情が異なります。細胞培養は体内と同じ約37℃で行われますが、ゼラチンはこの温度では溶けてしまうため構造を保てないのです。これに対してコラーゲンは、体温付近で固まるという特性を持ち、37℃でも安定した構造を保ちます。さらに、従来の細胞培養はシャーレ上で平面的に行われてきましたが、実際の人体は三次元構造のため、細胞を縦に積み上げることが必要になります。「温めると固まる」性質は、三次元細胞培養において重要な役割を果たします。
「細胞は自身では縦に積み上がることができないので、ジャングルジムのように三次元的に組み立てる技術が必要です。その足場としてコラーゲンは最適でした。」
ここに水溶性を実現したのが、TOPPANが大阪大学と共同で開発したコラーゲンマイクロファイバーです。コラーゲンを化学的に分解するのではなく、物理的に微細にすることで、容易に水に分散し37℃付近でも安定した培養環境として機能します。さらに「バイオインク」の材料として3Dプリンターでの成形にも対応しているなど、培養肉に最適な素材になりました。
こうした基礎技術を積み上げながら培養肉の研究開発は進められていきました。

「培養×食べ物」の可能性は無限大。食卓に新たな豊かさを
加藤は、培養肉自体は食糧問題や環境負荷削減などの社会課題解決だけにとどまらず、さらなるインパクトをもたらすと話します。
「食は非常に大事であり、自分が何を食べるのかというのはセンシティブな話題だと思います。そこに、新しい選択肢を提供するのは重要な視点だと考えています。」
既存の精肉の他に、タンパク質の代替方法には昆虫食、豆類由来の代替肉がありますが、そこに第四の選択肢として培養肉がある、そんな新しい食卓の姿を加藤は描いています。
さらに、今の仕事の楽しさを「0を1にするところ」にあると話します。
「世の中にないものを、アカデミアではなく、より社会に近い企業という立場で作っていることに、何ものにも代えがたいやりがいを感じています。さらにそれをTOPPAN独自の技術を活かして世の中に出していける可能性があるのは、TOPPANグループの一員としても、一研究者としてもおもしろいと感じるところです」
食品をつくるための研究は、TOPPANにとって初の試みといえます。ここに加藤が得意とする細胞培養の技術を掛け合わせることで、これまで世の中になかった新しい素材や価値を生み出す可能性もあります。「培養×食べ物」は無限大——加藤の挑戦は続いていきます。
※2026年2月公開。所属等は取材当時のものです。




